はじめに
過去の法律ネタで「おっとい嫁じょ」事件を取り上げたところ、そこだけ妙にアクセスがあるという現象がある。「おっとい嫁じょ」関連はなかなかに昔の日本にはやたらエロい風習があったという話としては興味深いものではあるのだが、その手の風習を語りだすと、とんでもないことになる。
薩摩の西郷隆盛なんかは、実家側が仕事をしてくれる女性が欲しいという理由で、西郷隆盛本人も知らないうちに結婚していたなどと言うエピソードもあるくらいなので、古い時代の結婚制度なんかは、かなり今の時代とは異なる。
あと、戦国時代なんかでは顕著なんだが、社会階層によって、結婚の仕組みが異なることだってある。たとえば、大名と地方豪族では、結婚相手候補が大きく違う。地方豪族の場合、有事の際に、夫の正室が家の主人としての代行者を務めることもあるために、結構、近親婚が成立していた(井伊直虎や真田信之の最初の正室なんかは良い例だろう)。逆に、大名やそれに準じる家臣クラスになると、結婚に政略結婚という要素が絡んで、外部から正室を取るようになる。真田信之や真田幸村の結婚相手が近親者から外部の大名関係者に変わるというのは、真田家そのものの立場の変化を示す格好の事例なのだ。
また、江戸時代でも、血統を重んじる武士階級と、農村共同体の維持を目的とする農村部では、当然性風習も変わってくる。農村部の場合には、農村共同体を守ることが優先されるが故に、「誰の子か」ということがあまり重視されずに、赤松啓介の社会学による著作に見られるような『夜這い』の文化が発達した。
というわけで、今回紹介するのは、古代バビロンの結婚オークション制度である。
そのうえで、結婚オークション制度こそが、現代の日本において有効に機能するのではないかという話をしてみたい。
古代バビロンの結婚オークション
ヘロドトスによると、紀元前500年ごろのバビロンでは、村ごとに年に1回結婚のためのオークションが行われていたという。
| 同じ財が同じ市場で正と負の両方の価格で売られる事例は、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが記した『バビロンの結婚市場』がある。花嫁候補を美しい順に並べると、最初は正の価格がつくが、一線を越えれば負の価格(持参金)がつく。 孫引き引用だが、出典は、『日経ヴェリタス』2012年7月29日号57面ブロゴスフィア |
一番わかりやすく端的にまとめたのがこの文章である。
より詳しく説明すると、結婚適齢期に達した女性は、年に1回、結婚相手を決めるオークションに「商品」として参加することが求められる。女性は美しい順番にオークションにかけられ、最も高値を付けた男性と結婚することになる。
ここで面白いのは、「男性が買うだけ」で済まないところだ。すなわち、0円より下があるということである。
あまりにも魅力がない女性は、価値がマイナスとなり、逆に女性側がお金を出して、男性に買ってもらうのである。
女性の人権を何だと思っているんだ、と思われるかもしれないが、これはこれで結婚の仕組みとしては今に通じるほどに合理的だ。すなわち、魅力のない女性は、結婚してもらうために、持参金を払うだけの経済力をつける必要があるのだから。これが実家に頼るのか、女性自身が稼ぐのかはとにかく。
ただし、どれだけマイナスになっても選ばれない女性がどうなるのかは定かではない。
なお、バビロンに代表される古代シュメール文明は、割と女性の地位が古代にしては高いことで知られている。バビロンのハンムラビ法典では、女性の側から離婚する権利や夫と死別した寡婦を擁護する条文などの女性の権利もしっかりと認められているのである。
結婚オークションを現代日本でやってみたらよい理由
人権問題的に人身売買なので、非常に難しいとは思うのだが、昨今の婚活事情を見る限り、日本でも婚活参加者限定で、この古代バビロンの結婚オークション制度を導入したほうが良いのではないかと思うことがある。
というのも、婚活女性側が、「自分の狙っている男性の価値を自分の価値」と勘違いしている傾向があるからだ。
そこには、日本の婚活高望み女性が、金目当てかつ、自分に隷属する男性を求めているだけで、相手の人間性が度外視されている実情がある。
「私は年収●●●万円の男性を狙っているから、年収△△△万円のあんたとは話すだけでも妥協」
などと、複数の女性から実際に言われたことがある。ところが、その女性たちがことごとく、無職であったり、低年収であったりする。私から見て年収の1/3以下、それどころか1/10以下の年収しかなく、家事もできずにお年を召した女性たちが、上から目線で、自分の価値を過大評価しているのを見るたびに、この手の婚活高望み女性の目を覚まさせるのには、結婚オークションしかないと思ったりしたりするのである。
婚活高望み女性を、専業主婦として背負う場合の日本人男性の経済的負担
では、実際に、婚活高望み女性とは、どれくらいの価値があるものなのだろうか?
純粋に現実問題として、高齢婚活女性や、子供を抱えたシングルマザーなんかは、結婚相手にとって経済的な重荷であるという自覚を持つべきだと思う。
母子家庭を見ても、普通に育てれば、子供一人を大人になるまで育てるのに2~3000万円かかると言われる。もちろん、教育費等にお金をかけなければ安く済むだろうし、時には子供が労働や性を売り物にすることで、貧困親に搾取される事件は多々ある。
でも、子供のために十分に働こうとしない、貧困母子家庭(母子家庭の過半数を超える)の母親は、子供の分だけで数千万円の借金を背負っているのと同じとみるべきだろう。
シングルマザーと結婚をするということは、他人の子供にも責任を持つということなのである。この視点は忘れられるべきではない。
また、意地でも専業主婦になろうとする高齢婚活女性とうっかり結婚しようものであれば、生活費や老後資金が見事に食いつぶされていく。
以前、ヤ〇コメにおいて、
「月に30万円しか貯金できないような低年収は、専業主婦を養うこともできない負け組男性」
などと言うバカげた主張をする方がいて、それに数百単位で「いいねボタン」が押されていたことがある。要するに、無職・低年収高齢婚活女性的には、働かず家事もできない専業主婦のために、30万円以上は必要と言っているのだ。
これはなかなか恐ろしい話ではある。「30万円貯金をする」というのは手取りが30万円以上が必要だ。仮に月の生活費を15万円としても、月の手取りは45万円。45万円の12倍だけでも540万円だが、これは源泉徴収を考慮すると、手取り540万円というのは年収で720万円を超える。
さらに言うと、「毎月30万円貯金」ということは、さらに追加でボーナスが加わるということである。年2回のボーナスで、月収の1.5倍がつくと仮定するとボーナスを含めた手取り額は675万円となり、およそ年収額は約930万円となってしまう。(手取りと年収の関係についてはこちらを参照)
上記のように、ボーナスも源泉徴収もわからない人たちは、まず無職、少なくとも正社員で働いたことはなかろう。
だが、これに「数百のいいねボタンが押される」ということは、月に30万円以上を女性のために使うことを最低ラインと考える、ボーナスも源泉徴収もわからない無職かそれに準じる存在が、ヤフ〇メの奥のコメントを数百人単位で見ているということである。
一体、現実には、この手の非現実的な女性がどれだけいるのか、想像するだに恐ろしい。
では、長くなったが、これまでの話を、婚活高望み女性を専業主婦として背負う場合の経済的負担額の根拠とみなし、40歳の高齢婚活女性と結婚する場合の経済的負担を月30万円と仮定して、考えてみよう。
2022年の女性の平均寿命は約87歳。つまり、47年間、毎月30万円の追加負担と考えると
47年×12か月×30万円=1億6,920万円
である。
婚活高望み女性を専業主婦として背負うということは、働きもせず、家事もせず、子供も産めずに、ひたすら男性に対して文句を言うだけの●●●を養うために1億6,920万円(以上)もの負債を抱えるのと同じことということでなのである。もちろん、これは金銭面に限ってのことで、さらに精神的労力的負担と、追加での経済リスクも生じる懸念がある。
終わりに
長々と書いたが、結婚オークション制度というのは、ある意味、極めて資本主義的な仕組みだ。
男性が買う側面だけが強調されて、男女差別だ、で思考停止するよりも、現代風に、男女双方がいずれも買い手にも売り手にもなれる制度を作って、現実の婚活に導入してみたらよいのではないかと思う。
強制参加なら人権侵害以外の何物でもないが、今の希望者だけが参加する婚活に限定してであればぜひとも、実験でもよいから、導入すべきだと思う。
そして、その結果はぜひとも見てみたい。
少なくとも働かない高齢婚活女性に対しては、この上ない現実を突きつけることになるだろうし、働くことのモチベーションを高めることにもつながるだろう。
婚活高望み女性が、非現実的な幻想に陥ったまま貧困に陥るというのは、生活保護費用を負担する社会にとっても、婚活高望み女性自身にとってもマイナスだ。もちろん、自業自得の自滅をした婚活高望み女性を救う責任は男性にはない。
なお、この制度が実現したとしたら、私個人は売り手でも買い手でも参加しないかなぁ。
多分、自分を買う女性はいないだろうという確信だけはある。
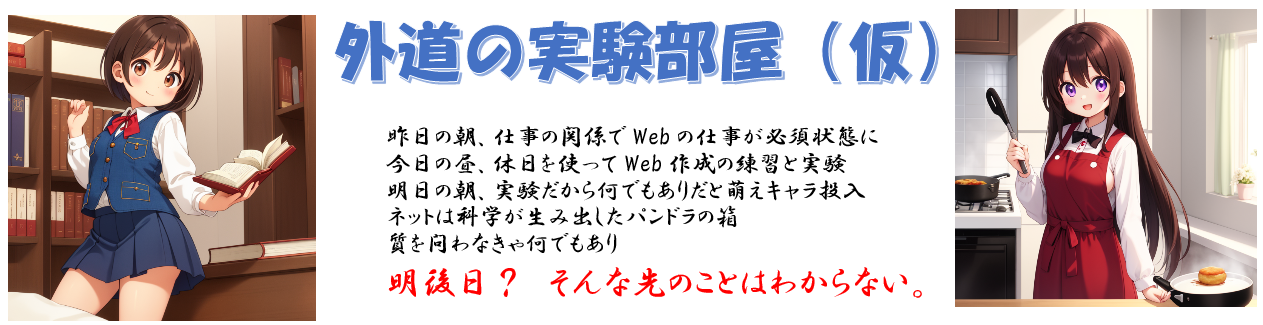




コメント